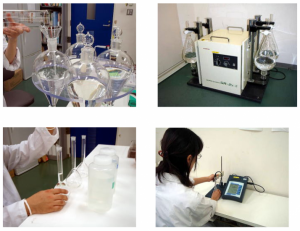夫や子も被害、不安消えず
西日本を中心に大規模な食中毒被害をもたらしたカネミ油症は、発覚から10月で50年になった。猛毒のダイオキシンが混入した食用油を食べて健康と幸せな日常を奪われた人たち。患者補償や未認定の「油症2世」の救済など、課題は尽きない。終わらない苦しみを見つめた。
東シナ海に浮かぶ長崎県・五島列島の漁村。木造平屋の仏間でカネミ油症の認定患者の女性(79)は静かに語った。「50年も月日が流れたのに……。悔しくて、忘れたくても忘れられない」
1968年春。29歳だった。漁師の夫と幼い3人の息子と5人暮らし。高度経済成長の余波で島にも活気があった。そんな頃、商店を営んでいた親戚から声をかけられた。
「安かよか油があるよ」
使っていた油より一升瓶(1・8リットル)で30円ほど安かった。10本入りの木箱で30本を買った。親戚や近所の人に頼まれて販売もした。油は焼酎やしょうゆの一升瓶に入っていて製造会社は分からなかった。
サツマイモやニンジンの葉、カボチャ、魚のすり身。ごちそうだった天ぷらを家族でよく食べ、客にも振る舞った。
ただ、油は加熱すると、カニが吹く泡のようにブクブクと泡が立ち、衣がベトベトになった。「おかしかね」。不思議に思ったが、別の油と混ぜながら、3本使った。
その年の夏、家族全員に症状が出た。女性は首やふくらはぎ、夫は背中、息子たちは頭にたくさんの吹き出物ができ、血尿や腹痛に悩まされた。
秋頃だった。受診した島の医師に「変な油を食べんやったね」と聞かれたが、家に戻るまで気付かなかった。「あっ、これか」。残っていた油を海に捨て、油を売ってしまった人たちに謝って回った。
家には当時、テレビもラジオもなく、68年10月の油症被害を伝えるニュースは知らなかった。カネミ倉庫(北九州市)の米ぬか油が原因だと知ったのは、その後に受けた県の検診会場だった。
「あの油はカネミじゃないと?」。確かめたくて油を薦めた親戚に面と向かって尋ねた。「自分は知らん」。謝罪の言葉はなく、親戚としての深い付き合いは終わった。
漁のたびに弁当を持たせた夫の症状は重かった。肌着は吹き出物から出る血や 膿 で染まった。小学生だった次男も布団から起き上がれなくなり、約1か月間入院した。「あの家から食べもんをもらうな」と陰で言われていたことは、遊びに来た親戚の子供から聞いて知った。ショックだった。
女性は30歳代で7回も流産。女の子を望んでいたが、医師に「母体が危ない」と説得されて諦めた。
一家は76年までに全員、油症患者に認定された。「毒入り油を食べさせ、家族を病気にさせてごめんね」。「分かっとって食べさせたんじゃなかけん、よか」。夫のこの一言で救われた。涙が止まらなかった。働き者で、よき理解者だった夫は2006年3月、73歳で亡くなった。 膵臓 がんだった。
カネミ油症では、1969年7月までに全国で約1万4000人が保健所などに被害を届け出た。今年3月末までに患者認定されたのは全国で2322人(死亡者含む)。カネミ倉庫の米ぬか油は、長崎県内の取引業者から島の商店などに配達され、五島市の認定患者は873人(同)に上る。患者補償は、国とカネミ倉庫から支援金など1人当たり年24万円と、医療費の自己負担分が支払われるだけだ。
子や孫の就職、結婚への影響を心配し、患者であることを隠し、症状があるのに差別を恐れて検診を受けない人もいる。女性も孫の将来を案じて名前を明かせない。
今も、手の震えやふらつき、不眠などに悩まされ、毎日、10種類以上の薬を服用している。「知らなかったとはいえ、油を食べさせてしまったことが悔しい」。半世紀たっても、健康への不安と自責の念は消えない。